年末調整システムの“正解”
“安全”かつ“低コスト”で乗り切る
国税庁の推進する年末調整の電子化に対応するための近道は、
2人3脚で進められる労務システムを導入することです。
導入前後のサポートとセキュリティ面において、
安全に導入できる年末調整システムを紹介します。
公開日: |更新日:
国税庁の推進する年末調整の電子化に対応するための近道は、
2人3脚で進められる労務システムを導入することです。
導入前後のサポートとセキュリティ面において、
安全に導入できる年末調整システムを紹介します。
公開日: |更新日:
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
ここでは「安全に乗り切る」をテーマに、セキュリティにおいては2段階認証のあるシステムを抽出しました。全従業員が使用するため、2段階認証の有無はセキュリティにおける選び方の指標となり得ます。同じ理由から、導入後に全員が使いこなせることも重要です。
そこで、無料トライアル期間のあるシステムを抽出し、最長期間を比較しています。
| 製品名 | 利用年額(税別) (従業員300人の場合) |
無料トライアル 最長期間 |
サポート体制 |
|---|---|---|---|
| オフィスステーション 年末調整 公式サイトから資料請求する 公式HPを見る |
150,000円 | 30日 | 社労士資格保持者、 実務経験者在籍の サポートデスク |
| 人事労務freee 公式サイトから資料請求する 公式HPを見る | 1,782,000円 | 記載なし | チャット、メール、 電話による相談可能 |
| SmartHR 公式サイトから資料請求する 公式HPを見る | 要問合せ | 15日 | チャットサポート |
| マネーフォワード クラウド給与 公式サイトから資料請求する 公式HPを見る |
31名以上は 要問合せ |
31日(1ヶ月) | チャットボット自動 応答、 チャット、 メール、 電話による 相談可能 |
※データは2020年9月時点で、独自調査によるものです。
※人事労務freeeは給与計算、マイナンバー管理、法定三帳簿対応、経費精算連携、労務手続き、勤怠打刻記録がセットとなった料金(ベーシックプラン)です。
※SmartHRは人事情報管理、自動書類作成、電子申請、マイナンバー管理、web給与明細、カスタム社員名簿がセットとなった料金(スタンダードプラン)です。
上記で紹介した、導入前後のサポート面、セキュリティ面においておすすめできる4製品について、従業員数別の年間コストイメージを個別に紹介していきます。
併せて、各製品のセールスポイントについても触れていますので、こちらを見ながら各社の導入事例や導入企業を見比べていくと、スムーズな年末調整効率化システム選定の役に立ちます。

| 従業員規模 | 費用 |
|---|---|
| 100名 | 50,000円 |
| 300名 | 150,000円 |
| 500名 | 250,000円 |
| 1000名 | 500,000円 |
※年末調整に関するシステム導入の料金

| 従業員規模 | 費用 |
|---|---|
| 100名 | 582,000円 |
| 300名 | 1,782,000円 |
| 500名 | 2,982,000円 |
| 1000名 | 5,982,000円 |
※ベーシックプランの料金

| 従業員規模 | 費用 |
|---|---|
| 100名 | 要問合せ |
| 300名 | 要問合せ |
| 500名 | 要問合せ |
| 1000名 | 要問合せ |
※料金データは2020年9月時点、独自調査によるものです。

| 従業員規模 | 費用 |
|---|---|
| 5名 | 35,760円 |
| 10名 | 119,760円 |
| 20名 | 287,760円 |
| 30名 | 455,760円 |
※スモールビジネスプランの場合
※従業員31名以上の料金については、個別にお問い合わせください。
2020年より年末調整の電子化が始まりました。電子化を導入するメリットは年末調整にかかる時間や手間を短縮できることにあります。
まずは電子化に対応したシステムを導入し、税務署へ電子化の申請を行ってください。会社側の準備だけではなく、マイナンバーカードの取得など従業員への準備を早めに進める必要があります。

保険会社等


控除証明書


従業員

各種申請書の
やりとり

人事/総務


税額計算
電子化その1
控除証明書の交付がデータに!
電子化その2
保険料控除申請書等がペーパーレス化!チェックや保存当の負担が軽減!

保険会社等


控除証明書
電子化その1
控除証明書の交付がデータに!


従業員

各種
申請書の
やりとり
電子化その2
保険料控除申請書等がペーパーレス化!チェックや保存当の負担が軽減!

人事/総務


勤務先
国税庁の取り組み
「年末調整の電子化」の定義は、大まかに以下の二項目における電子化を指します。
年末調整の電子化を進めるためには、従業員側はマイナンバーカードの登録や各保険会社への手続き、事業者側は税務署へ手続きが必要となります。

保険会社等


控除証明書
データまたは紙で
控除証明書を受け取る


従業員

データ入力

年末調整システム

データの提出状況チェック

勤務先
控除証明書のみシステムによっては紙での提出が可能。この場合、従業員側における電子的交付の手続周知が必要ない
【従業員側の導入メリット】
質問に答える入力フォーム方式等でわかりやすい
【勤務先側の導入メリット】
従業員側の入力不備はシステムがチェックする。提出状況を一日で把握できる

保険会社等


控除証明書
データまたは紙で
控除証明書を受け取る
控除証明書のみシステムによっては紙での提出が可能。この場合、従業員側における電子的交付の手続周知が必要ない


従業員
【従業員側の導入メリット】
質問に答える入力フォーム方式等でわかりやすい

データ
入力

年末調整システム

データの
提出状況
チェック

勤務先
【勤務先側の導入メリット】
従業員側の入力不備はシステムがチェックする。提出状況を一日で把握できる
民間の年末調整システムの主な仕組み
民間の労務システムを使用すると、国税庁が推し進めている年末調整電子化に対応するだけでなく、年末調整業務の効率化を図ることができます。多くの民間システムに組み込まれているのは従業員による情報入力の簡略化です。
たとえば、スマートフォンやPCから申告できるため提出の手間が減ります。また、担当者はシステムで提出状況を確認できるため、年末調整の進捗ステータスが分かりやすいのです。
また、年末調整の電子化においては、従業員に対するマイナンバーカードの取得を義務付ける必要があり、これにかかる現場からの不満や対応不備が予測されます。民間のシステムであれば、従業員は現状どおり紙の控除証明書を受け取りながら、社内の書類のみペーパーレスにすることも可能です。

もっとも大きいメリットは今まで添付書類として提出していた「各種保険の証明書」も電子申請できるため、従業員の提出準備が楽になります。
また、今まで添付提出していた「残高証明書」や「住宅借入金等特別控除申告書」も電子申請できるため、証明書の転記ミスが起こりにくいでしょう。管理者は申告書を郵送する必要がなく、添付書類の不備などで個別対応する負担が減ります。
年末調整業務を電子化すると、申告書の配布や回収、記載内容のチェック、計算など、これまで人事部や経理部を悩ませてきた煩雑な業務について、目視や手作業による記入漏れや数え間違いなどのミスを格段に減らすことができます。
最も大きいメリットとしては、申請に必要な各種証明書の内容を転記する必要がなくなるため、申告がラクになるという点が挙げられます。

電子化の準備
年末調整の電子化するためのシステムを導入する必要があり、どのシステムを導入するか選定を行います。その後、所轄の税務署へ電子申告の申請をしてください。
担当者の準備
どの電子化システムを導入するか選定し、従業員へのマイナンバーカード取得を周知します。
従業員への周知
従業員がマイナンバーカードを取得しなくてはいけません。取得後はマイナポータルの初回ログインし、e-私書箱の開設まで完了します。また、利用している保険会社や銀行の電子証明書の発行依頼をお願いします。

マイナポータルとは政府が運営しているオンラインサービスで、年末調整で提出する生命保険の控除証明書をマイナンバーカードと連携してマイナポータルから取得することができます。今まで控除証明書は所定期間に郵送で届くため、提出日まで各自が保管する必要がありました。
また、控除証明書を紛失してしまうと再送手続きに2週間くらいかかっていたため、マイナポータルを活用した一括ダウンロードは申請者の負担を軽減してくれます。

担当者の準備
電子申請を行うシステム選定をおこない、給与システムと連携する方法を確認してから導入するシステムを決めます。その後、従業員へ利用する年末調整のシステムを周知し、税務署へ電子申告の届け出をしてください。
従業員の準備
年末調整の電子申請を行うためにはマイナンバーカードを取得し、専用のICカードリーダーが対象のスマートフォンを用意します。そして、マイナポータルで電子証明書を発行するための事前設定を行い、社内の専用システムを取得してください。

年末調整の作業効率を推進する4つの手段をご紹介しています。まずはペーパーレス化した年末調整システムを導入することで、管理者は郵送や回収の手間がかかりません。
また、専門会社に年末調整の作業だけアウトソーシングする方法や、社会労務士に日々の給与計算をサポートしてもらう対策もおすすめです。税理士のプロである税理士に年末調整の申告を依頼する方法もありますが、社労士との業務範囲が違うため気をつけて委託してください。
年末調整業務の効率化ができる労務管理ツールを紹介します。各製品について料金設定は異なりますが、ここでは年末調整に関するシステムが使用できるプランにおける「1人あたりの年間料金(2020年9月調査時点)」に着目し、各製品の費用感のわかるデータとして紹介していきます。
それぞれ初期費用や従業員数ごとの割引・割増など複雑な料金設定があるため、正確な料金については各社への問い合わせをおすすめします。
※年末調整を含むプラン
導入後のサポートが手厚い
オフィスステーションはアラカルト型の製品で、年末調整や給与計算などのソフトを必要に応じて導入できます。導入前後に感じられる使いやすさがあり、例えば、サポートデスクには待ち時間0分で必ずつながる万全さです(2020年9月調査時点)。
※有料プラン
認定アドバイザーがサポートしてくれる
ジョブカンは、「ジョブカン認定アドバイザー」が適切なアドバイスをしてくれる年末調整ソフト。社労士、税理士、会計士などが認定アドバイザーとして所属しており、コンサルティングを受けることもできます。シリーズ累計で50,000社の導入実績がある定番ソフトです(2020年9月調査時点)。
※ベーシックプラン
業界トップクラスのセキュリティ運用体制
freeeは、すべての情報を暗号化して通信し、国際認証である「TRUSTe」を取得。セキュリティ体制は業界トップクラスともされています。人事労務管理全般のためのサービスなので、料金はほかのサービスに比べて高くなっています。
※給与計算システム導入費用
システム運用の定着までしっかり
サポートしてくれる
jinjerは、導入後も運用が定着するまでは1社ずつしっかりとサポートしてくれる手厚さが特徴です。導入する企業に最適な設定や運用方法をアドバイスしてくれる上に、導入後の不安についても経験豊富なスタッフがコンサルティングしてくれるサービスとなっています。
※料金データは2020年9月時点、独自調査によるものです。
提携社労士のコンサルが受けられる
スマートHRは、2020年1月現在で20,000社以上が導入しているシステムです。提携社労士がコンサルティングをしてくれるので、業務効率改善を徹底的に進めたいケースには最適です。31種類もの外部サービスとの連携も魅力となっています。
低コストで利用できる年調ソフト
年末調整の電子化システムだけを利用したい方に適しているのが年調ヘルパー。ペーパーレスの年末調整を促進し、また税法改正に自動で対応してくれるというメリットもあります。
※年末調整を含むプラン
国際水準のセキュリティ
奉行Edge (オービック)は、SOC1、SOC2、ISO27001といった国際規格を満たすセキュリティを備えたサービスです。また多様なサポート体制があり、電話、メール、FAXで気軽に相談できるという安心感があります。
一問一答でかんたんに申告書作成!
年末調整Web申告(さくら情報システム)は、500名から利用できる年末調整システムです。一問一答型のWeb申告システムで、簡単に申告書を作成することができます。また提出が遅れている従業員への督促も簡単にできるのが便利なところです。
写真をアップデートすると入力してくれる
簡単年調は、保険料の控除証明書を写真でアップすると、エコミック社がデータ入力を代行してくれるというもの。他社のサービスとは経路が違いますが、年末調整を簡単にしてくれることに変わりはありません。
※勤怠給与ソフト導入の場合
どのプランでもサポートが無料!
ジョブルポは、自動仕分けや年末調整の申告など幅広くサポートしてくれる会計ソフト。契約プランの種類に関わらず、無料でサポートを利用できる安心感があります。困ったことがあれば、専門スタッフが電話で相談に乗ってくれます。
※スモールビジネスプランの場合
労務管理全般をサポート
マネーフォワードは、数多くのクラウド給与管理システムと連携して年末調整を効率化してくれるサービスです。会計ソフトとして幅広い分野をカバーするため、ほかのサービスに比べて費用は高額となっています。2段階認証の採用など、セキュリティの強化も進んでいます。
給与管理の定番ソフト
弥生給与20は、会計ソフトの定番である弥生シリーズのサービス。「あんしん保障サポート」を利用すれば、次年度のシステムは無償で提供され、法改正などのシステム更新の際も追加費用が不要。また上位プランでは幅広いサポートが受けられるという特徴も。
クラウド型の業務管理ソフト
EdgeTrackerは、マルチデバイスで利用できる業務管理ソフト。クラウド型なので、外出先からも利用できる利便性のあるサービスです。操作などがわからない場合は、パソコンの画面を共有してサポートしてくれる「オンラインサポート」も用意されています。
簡単に電子申告ができる
S-PAYCIAL(鈴与シンワート)は、年末調整の電子化システムに特化したサービスです。クラウドで利用できるので、マルチデバイスに対応しており、いつでも年末調整の電子申告ができます。紙ベースより申告しやすく、業務効率に役立ちます。
専用アプリから年末調整申告ができる
年末調整申告支援システムは、専用アプリを使って年末調整の申告をするソフト。法改正への対応も早く、管理者の作業負担を軽減してくれるます。料金やセキュリティ体制についてははっきりした記載がありませんが、毎年9月の法改正にはしっかり対応しています。
SSL通信で強固なセキュリティ
ポケット給与は、SSL通信による暗号化で、セキュリティを強化している年末調整システムです。給与明細書の印刷や仕分け、配送処理を自動化してくれる上に、ペーパレス化を実現してくれます。自社向けの帳票カスタマイズも可能。
年末調整以外にも広く使えるシステム
年調・法定調書の達人は源泉徴収、保険料等の控除申告書を帳票イメージで入力できる、業務を知り尽くした設計が売りのシステムです。年末調整だけでなく、他のソフトや既に導入しているシステムと連動・連携することで多種多様な帳票作成が可能です。サポート体制も充実しています。
WEBブラウザで、スピーディーかつ正確なシステム
三菱 ALIVE SOLUTION YAは、年末調整でこれまでかかっていた作業を簡略化することができるシステムです。紙の申告書ではなく、WEBブラウザへの直接入力なので、ミスを減らすことができ、人事総務部が年末調整に関してかけていた手間と時間を大幅に削減することができます。また、「前年度申告データコピー機能」を使えば、一からデータを入力し直す必要がなく、変更箇所の修正だけで申告書の作成が可能です。安全性に関しても、「オンプレミス型」の高セキュリティーデータ管理システムを採用しているので、マイナンバーやご家族の個人情報も安心して管理することができます。
WEBブラウザだけでOK!ラクラク年末調整
電算の年末調整申告支援システムは、WEBブラウザ上で、年末調整に必要な各種申告書に入力し、担当者が一括で管理できます。そのため、事前に申告書を配布する必要がなく、また、前年度の申告書データを流用することが可能なので、入力ミスを減らすことができます。また、保険料控除額の自動計算やチェック機能を使うことにより、申告書作成後の事後チェックを省けます。面倒なソフトのインストールもないので、使い勝手も好評です。
年末調整申告をスピーディに!
JOEの年末調整申告システムは、クラウドシステムを採用しているため、ソフトをインストールする必要がなく、簡単な設定で利用することができます。紙媒体の書類にかかる手間やコストを削減することで、担当者の作業を簡略化することも可能です。その他、スケジュール管理機能なども並行して利用することで、年末調整申告業務をスムーズに行うことができます。
クラウド型で操作性に優れた給与計算ソフト
フリーウェイ給与計算は、クラウド型で、ダウンロードからアップデートまで手軽に行える操作性に優れた給与計算ソフトです。従業員数5名までは無料プラン、それ以上は月額1,980円(税抜)の有料プランとなります。従業員数に応じて自社に適したプランを選択できるので、負担にならずに導入できることが魅力です。また、計算ソフトが苦手な方でも、簡単に操作できるようマニュアルや説明動画も充実しているので、安心して導入することができます。これまで手間と時間をかけてきた年末調整や給与計算を、効率化するのにオススメのソフトです。
サポートが魅力の「給与アウトソーシングサービス」
CYBER XEED 給与は、WEB画面からデータ管理が可能な「給与アウトソーシングサービス」です。普段の従業員の給与管理はもちろんのこと、忙しくなりがちな年末調整など、社内での業務を軽減することができます。 また、専任オペレーターによるサポート体制も充実しているので、パソコン操作が苦手な方でも安心して利用可能です。データ管理もプライバシーマークと取得したサービスセンターで行っているので、セキュリティ対策も万全です。
※年末調整を含むプラン
リーズナブルに利用できる年末調整サービス
年末調整用の機能に特化したシステムが特徴的であり、他の機能が搭載されていないことから、シンプルでリーズナブルな料金プランが設定されています。従業員が直接web入力で申告することを想定して設計しているため、誰でもわかりやすく利用できます。
※年末調整を含むプラン
情報共有や管理の全てをクラウド上で行えるシステム
電子上のデータ交換機能により、社内業務を全般的にクラウド上で管理することが可能です。年末調整機能を含め、社内システムを全て一元化して社内業務を電子化し、従業員の負担軽減にも繋がります。
※年末調整を含むプラン
社会保険労務士が作った給料計算システム
労働・社会保険の専門知識を豊富に持った社会保険労務士が制作したソフトであり、給料明細やタイムカード入力といった様々な機能が搭載。年末調整から日々の勤務までの煩雑な業務を、トータルでこなします。
クラウドで簡単な操作性
給与計算と給与データの活用をサポートする同システムは、クラウド型によりどんな環境でも簡単にアクセス・利用できます。クラウドで使用できる基本サービスに加え、業務代行サービスとなるオプションを組み合わせて利用者ごとに柔軟な使い方ができるのが同システムの特徴。必須登録項目や色分け、確認や警告ポップ表示など…誰もが分かりやすく使える画面・機能が魅力です。
マイナンバー管理までトータルサポート
法定調書関連業務をより効率的に作成・管理するシステムです。報酬関連の支払調書や不動産の支払調書など、対応している帳票が数多いのが特徴的。専用システムを利用せずに電子申告が可能になる機能性の他、専用ツールを利用することでマイナンバーを安全な環境で管理することも可能です。プランはクラウド・サブスク・パッケージの3種類から選択できます。
雇用形態の多様化にも柔軟に対応
正社員から派遣社員、契約社員など…多様な雇用形態にも対応できることから、様々なメンバーに合わせた給与パターンを作成・管理可能です。会計士や社労士とも給与データ連携を行えます。月次の給与計算から年末調整までの処理をシステム1本に一元化したことにより、再入力や転記が不要。従業員を多く抱えている企業でも迅速な処理を可能とし、ネットワーク対応で複数名での同時起動も行えます。
ワンクリックでの電子申告が可能
1つのシステム内で、源泉徴収票データをcsv形式にて読み込むことにより、ワンクリックで電子申告が可能になります。必要な手続きは全てシンプルで分かりやすいメニューにされているため、知識やノウハウがないユーザーでも事前準備から申告データ作成・申告までが簡単に完了します。10年間にわたってデータを保管しておけるため、過去の履歴をいつでも確認することができます。経理についての専門知識がない人はもちろん、PC作業が苦手な人にもハードルが低いのが魅力のシステムです。
法定調書関連業務を一元管理可能
各種支払調書や年末調整業務をはじめとする、法定調書関連業務を一元管理・処理する機能を持ったシステムです。支払調書の作成や、それを基にした源泉徴収合計表や内訳書を作成できるなど、経理関連の業務の多くをシステム化して効率化することが可能。顧問先や取引送付用のタックシール印刷にも対応しています。システム登録情報を従業員に渡すだけで年末調整にかかわる煩雑な業務が完了。電子申請も簡単に行える他、各自に確認・修正してもらう「年末調整準備シート」の用意で、年末調整が簡略化されます。マイナンバーの保管・利用時の安全管理措置も万全に行われており、従業員のデータベース化に繋がります。
導入事例についての記載なし
ユーザーが迷わずに申請までできるサービス
申告者が迷ったり間違えたりせずに申告できることを狙いとしてつくられたシステムで、事前準備から進捗管理・給与計算用データ作成までを一括で行うことができます。クラウドシステムにより、パソコンからでもスマートフォンからでも利用可能。一連の業務が電子化・自動化されることで、煩雑な業務をシンプルに完了させます。レイアウト構成は実際の申告書をイメージしたものであるため、これまで紙で申告していたユーザーにも馴染みやすいのが特徴。
年末調整のシステム化を進める上で、「なぜ年末調整を行うのか?」「間に合わなかった場合どうなるのか?」を理解しておきましょう。

年末調整とは、文字通り年末に行うべき税金の調整のことです。会社勤めの人がその一年で得た収入と、支払った所得税の額を計算して、税金の払いすぎや未払いを精算するのが年末調整の役割です。
人によって働く会社や働き方が違いますから、納税の額や方法も異なります。こうした一人ひとりの納税の「ズレ」を見つける…というのが、年末調整の狙いなのです。
年末調整で具体的に必要とされるのは、所得額や所得税を示すための書類や、控除を受ける配偶者がいる場合にその証明をする書類など。会社員であれば従業員全員の所得税を会社側が計算してくれますが、一人ひとりの家族構成などによっては、個別に提出すべき書類も存在します。
源泉徴収とは?
収入や所得税額を計算して納税額のズレを正すのが、確定申告の役割です。ただし一人ひとりが確定申告をしていては時間も手間もかかりますから、会社勤めの人は会社側があらかじめ所得税額の大まかな金額を計算し、従業員の毎回の給与から天引きしています。こうして会社から税金にまとめて支払われている従業員たちの所得税が、「源泉徴収」と呼ばれるものです。
つまり仮払いで収められている税金のことです。本当に支払うべき所得税額は年末に決定しますから、控除や所得税の計算方法の違いなどがあった場合には、年末に源泉徴収で「取られすぎ」ている分も発覚することがあります。
そのため会社を経営する経営者は、従業員たちの毎年の所得税額が確定する年末に、源泉徴収による納税額と正しい所得税額のズレを見つけなければならないのです。
年末調整の対象になるのは?
年末調整をする必要があるのは、源泉徴収をされている会社勤めの従業員です。「所得」のある人には所得税の納税が義務付けられていますが、個人事業主は自分で確定申告をして納税を行いますから、会社勤めのケースとは異なります。
会社の経営者は、自社で働いて毎月源泉徴収を行っている従業員たち全員に対して、従業員分の年末調整を行う必要があるのです。社員一人ひとりの所得控除を確認するために、社員には「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」などの各種申告書の提出を求める必要があります。
年末調整の後は、必要に応じて天引きしすぎた分の源泉徴収額を従業員に還付します。逆に源泉徴収額が年末に確定した所得税の額よりも少なかった場合には、その差額を従業員の給与から天引きします。
一連の源泉徴収税の計算と清算が終われば、「源泉徴収票」を作成して従業員に配布します。

年末調整は年末に所得税が確定するために行われるものです。そのため毎年11月頃から12月頃には、企業側から年末調整の書類を各従業員に配布し、案内を通達するのが一般的。
ところが年末調整の作業は経営者側からだけではなく、従業員側から見ても煩雑なものであり、従業員によっては書類の提出期限を忘れてしまうケースもあります。従業員の中に提出書類の「出し忘れ」や「遅れ」が生じた場合には、いくつかのデメリットが生じます。
結論から言えば年末調整のし忘れも後からカバーできますが、とても複雑な手続を踏むことになるため、可能であれば年末調整は期限内に行いましょう。
税金を払いすぎてしまうかも
まず年末調整とは、会社員や公務員が得た給与から天引きされている、源泉徴収額に払い過ぎがないかをチェックするためのものです。1年間で支払った源泉徴収額と、従業員の給与や控除額を計算して照らし合わせることで、源泉徴収額に過不足がないかを確認するのです。
一概にすべての従業員が、とは言えませんが、年末調整を行うことで支払いすぎた源泉徴収額が還付されるケースは少なく在りません。年末調整できちんと控除できる額を示すことで、還付される額が増える可能性があるのです。
ですから、もしも年末調整をし忘れてしまった従業員がいたら、その人は本来還付されていたかもしれない源泉徴収税が還付されず、税金を支払いすぎてしまうかもしれません。場合によっては損に感じる額が還付されていたかもしれませんから、年末調整は忘れずに行うのが良いでしょう。
遅れたときは「確定申告」を出す
もしも年末調整を忘れたけれど還付を受けたいのであれば、「確定申告」を行いましょう。確定申告は翌年の3月15日まで申請できますから、各種控除を受けるための証明書類や、会社から発行される「源泉徴収票」を用意していれば、会社員でも公務員でも確定申告書を作成することができます。
ただしこの場合の確定申告書作成については、年末調整と違って会社側が引き受けてくれませんから、従業員が自分で画定申告書を作成して税務署に提出する必要があります。
この確定申告の手順はシンプルですが、詳しくない人がやると手間に感じる作業や複雑に感じる箇所が多くあります。素人が一から計算する場合にはミスが生じる可能性がある他、控除漏れも生じる可能性があります。面倒な確定申告をしなければならない、というのも年末調整を忘れるデメリットの一つです。
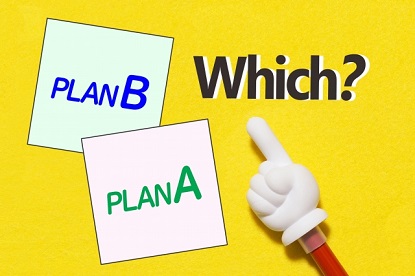
従業員の生活や会社の経営に直接かかわる年末調整ですが、人の手ではなくシステムに一任することも可能です。ただしシステムを導入するのであれば、使用料金と性能が釣り合っているかどうか、「費用対効果」が重要。
年末調整システムを選ぶ際に、特に注目したいポイントについてチェックしていきましょう。
高度なセキュリティ
年末調整を行う際には、従業員や会社についての様々な個人情報を取り扱います。従業員の働き方や労務情報など、かなりプライベートな情報も取り扱いますから、年末調整システムには高度なセキュリティ性が求められるのです。
年末調整システムの多くは、従業員の一人ひとりが自分でシステムにアクセスして情報を入力していくタイプのものです。そのため、従業員にスキルや知識がなくても情報の安全性が保たれるタイプのシステムであることが非常に重要。
機能性が一般的なシステムでも、セキュリティ体制についてよくチェックしてシステムを選びましょう。二段階認証はあって当たり前、他にも情報の暗号化や、システムを運用している制作会社側が行っているセキュリティ対策についてもよくチェックしておきましょう。
【従業員全員が】使いこなせるか
年末調整システムによる年末調整を実施するということは、年末調整のペーパーレスを行うということです。従業員の全員が利用するわけですから、どんな人であっても簡単・シンプルに利用できる操作性が望まれます。直感的な操作性であることや、ユーザーインターフェースの親切さなどに注目してみましょう。
また、従業員が使用するデバイスにも対応できる必要があります。スマートフォンやPCなどからのアクセス体制についてもチェックしてみましょう。
できれば資料請求をして詳細に操作性に確認した上で、無料トライアルなどを利用して実際に使ってみるのが理想です。一人だけではなく、複数人で使ってみましょう。
導入後のサポート体制
導入後には必ずと言って良いほど、様々なトラブルが発生します。従業員の中にはシステムの使い方が分からないことがありますし、思わぬ誤操作や修正対応が必要になるケースも生じるでしょう。
年末調整システムによっては、メールやチャット、サポートデスクで導入後のサポートを行ってくれるものもあります。他にも、実際に開発元のスタッフが自社内に在籍し、システム使用のレクチャーや質問対応をしてくれるシステムも存在します。「自社に限って」とは考えず、導入後にどんなサポートが受けられるのか確認しておきましょう。
人事や経理、総務担当者のために、年末調整でよくある質問をまとめました。年末調整で聞かれるパターン10選をピックアップして、質問形式でそれぞれ解説しています。年末調整のポイントをおさえておくと、従業員から質問されてもすぐに回答ができるでしょう。
年末調整の原則として、給与の支払者は年末調整を実施しなくてはいけません。ただ、年収2,000万円以上の方や「扶養控除等(異動)申告書」を見申請の方は年末調整の対象外です。今回のように例外ではない従業員の場合は、控除のない状態で年末調整だけ行えば良いでしょう。その後、ご本人が確定申告を行うことで、各種控除の対象となります。
控除証明書がなくても年末調整を行うことは可能です。しかし、生命保険会社の控除証明額を記載しなければ、所得控除される正確な金額は算出できません。年末調整は可能ですが、控除額によって追徴課税される場合があるため、従業員に控除証明書を再発行するよう依頼してください。
前職の源泉徴収票がなくても年末調整は可能ですが、間に合わなかった場合はご本人が所定期間に確定申告を行う必要があります。
いつ手元に届くか従業員に確認し、年末調整の社内集計に間に合うか確認しましょう。もし、社内期日に前職の源泉徴収票が提出できない場合は、そのまま年末調整を行ってください。
複数の企業に勤めていた場合は、それぞれの勤務期間を確認してください。原則としてアルバイト雇用なら8カ月以上で、正社員の場合は1週間以上の雇用期間があれば、勤務日数にかかわらず源泉徴収票が必要です。対象企業分の源泉徴収票が間に合わない場合は社内では年末調整だけを行ってください。その後、ご本人から確定申告を実施してもらいましょう。
平成29年度よりマイナンバーカードの運用が改正されたため、以下の項目を記載していれば「扶養控除等(異動)申告書」へのマイナンバーカードの記載が不要になりました。
従業員にふるさと納税の証明書を返却し、年末調整で発行された源泉徴収票を使用して所得税の確定申告を行うよう伝えてください。その際、ふるさと納税は寄付金控除にあたるため、会社で行う年末調整では対応できないと理由を伝えましょう。初めて住宅ローンを利用した方や医療費控除の対象者も同じ考え方になります。
会社は従業員から受け取った源泉徴収票税を税務署へ納めていますが、年末調整で対象の従業員に還付金を支払う場合があります。こちらは一見すると二重払いのように見えますが、会社が税務署へ源泉徴収票税を納めるときに従業員へ還付した金額分を相殺しているので問題ありません。
住宅借入金で間違えやすいのが住宅ローンの借り換えを行った場合で、申告書の「居住開始日」と「借入日」の日付が離れているのが目印です。借り換えローンのときは旧ローンの残高を新ローンが上回ると「残高証明書の年末残高」を利用できないため、適切に案分計算を行いましょう。
例として「地震保険料控除証明額5万円 、旧長期損害保険料証明額2万5000円」と1枚の控除証明書にかかれている場合は、どちらか1つの控除額しか年末調整の控除対象になりません。
こういった場合は、少しでもお得になる項目を選択して年末調整を算出してください。
国外に住んでいる親族へ送金した場合、年末調整の対象となるかの判断ですが、特に送金回数は定められていません。そのため、国外の親族へ1回だけの送金であっても、控除対象扶養親族として年末調整を行って構いません。もし送金した金額が少額でも、「生活費」または「教育費」と回答されれば問題ありません。
まとめ

年末調整の電子化とは、基本的にペーパーレスによる業務負担の軽減、書類保管コストの軽減を目指した取り組みです。
年末調整業務のペーパーレス化を推し進めていけば、人事労務担当者にとっても業務負担上大きなメリットがあるわけです。ペーパーレス化を進めるための第一段階として、国税庁の推し進める年末調整の電子化への対応があります。
ペーパーレス化による業務負担軽減に向けて、第一段階から進めていけるパートナーがいれば心強いはず。このサイトでは、労務管理システムを単なる「ソフト」としてではなく、年末調整業務のパートナーとして付き合っていくことが重要であると考えます。